【Page6】84年85年の鈴鹿4時間耐久レースを連覇!!
掲載日:2009年11月27日 特集記事 › V4「400」全盛、あの時代。
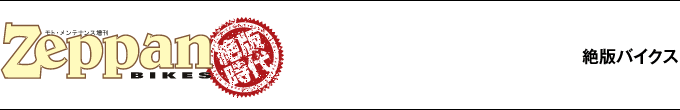
記事提供/2008年11月27日発行 絶版バイクス Vol.2
今まさに蘇ろうとしている初代V4レーシングモデル。
HONDA HRC VF400RK 1985 by RT HONEYBEE
1980年代前半に販売台数のピークを迎えたバイクブームは、おびただしい数のニューモデルと、当時風に言えばギャルライダーを生み出した。これらと並行して流行したのがレースである。
そこには街のバイク好きが、ある日突然ヒーローになれるチャンスがあり、それを求めた若者達の最高の舞台が、鈴鹿4時間耐久ロードレースだった。
一方、バイクブームの頃は、レースで成績を残すマシンは速い=売れるという方程式が通用したため、メーカー系ワークスチームが直接乗り込むことはないまでも、4耐はそこに関係の深い、息がかかったマシンが火花を散らした。
1984年。VF勢最上位の予選8番手からスタートし、後半には雨となる荒れた展開の中、終始スリックタイヤで走り逃げ切ったのが斉藤兼一/山崎政俊のライディングで優勝を飾ったチームハニービーのVF400Fだ。1983年登場のVFが、1シーズン遅れでつかんだ栄光であり翌85年も優勝。
シオハウス塩畑さんの手によって、20年以上の時を経て再び日の目を見たVFは、耐久だけでなく各種スプリントレースにも参戦していた。そのため完全な84年4耐仕様ではないが、ショップチームのレースマシンとしては比較的当時のフォルムと仕様を残している。
登場から25年以上を経て、さすがに丸パイプフレームのVFを見る機会はほとんどない。しかしこのフォルムを見ると、熱かったバイクブームを思い出す絶版車好きもいるはずだ。VF400FからVFR、そしてRVFと熟成されたホンダV4黄金時代の幕開けを飾ったマシンは、静かに復活の時を待っている。
当時の大人気コミック「バリバリ伝説」でも、主人公の巨摩郡が峠のCB750F時代を経て、スズキGSX-Rで鈴鹿4耐に優勝するストーリーが描かれている。若手ライダーの登竜門として、4耐はそれほど影響力が大きかった。ちなみに1984年、決勝進出61台を目指してエントリーした台数は400台以上と、文字通り狭き門だった。そしてこのうちVFは92台を数えたという。勢力的には1983年12月にデビューしたCBR400Fの107台には及ばないが、熟成の進んだVFは頼れる相棒だったようだ。

タコメーターと水温計のみというシンプルなメーターは、HRC製キットパーツ。

前後ホイールは、当時CBR400F用を流用したとされており、ディスクローターもリジッド式。

キャリパーはフルカウルタイプのインテグラやCBRと同様のピンスライド式の2ポット。左アウターチューブ下端には、ブレーキング時のノーズダイブを抑制するTRACのノブもある。

イグナイターはHCR製パーツがあったが、点火コイルは純正パーツを使用する。

空冷のCBXに対して初めて水冷を採用したVFは、サーキットでの水温上昇が課題となった。そこで ハニービー車では、ラジエターコアの厚みを増して、さらにフロントシリンダーを挟み込むような2階建てラジエターを装着。

カムシャフトとマフラーはHRC製キットパーツを用いたが、基本的にはエンジンはスタンダード状態で使用した。当時の資料によれば、パワーは62~63馬力、パワーバンドは1万1000~1万5000回転と広く、4耐決勝中は1万4000回転を上限としたとのこと。
- Page1V4「400」全盛、あの時代。
- Page2あの時代のホンダV4が、熱く見える!!
- Page3初期トラブルが少なかったのもV4/400ccの特徴だった
- Page4ホンダV4エンジン
- Page5ホンダ RVF 1996
- Page684年85年の鈴鹿4時間耐久レースを連覇!!
- 【前の記事へ】
【Page5】ホンダ RVF 1996 - 【次の記事へ】

V4「400」全盛、あの時代。
こちらの記事もおすすめです
- 2013 AMA スーパークロス ラウンド17(最終戦) ラスベガス NV レースレポートモトクロス

- スズキ新型GSX-8T/8TT 新商品説明会 速報レポートフォトTOPICS

- 【スズキ GSX-S1000F 試乗記】これ一台ですべてをまかなえる、ある種の”アガリ”バイク試乗インプレ・レビュー

- 【スズキ GSX-S1000GX 試乗記】ド根性スタイルには疲れた。でも刺激欲は枯れてない。そんなアナタへ試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-R600(2015) – 20年以上の進化熟成を重ねたミドルスーパースポーツ試乗インプレ・レビュー

- 2014 AMA スーパークロス ラウンド17 ラスベガス NV レースレポートモトクロス

- 2013 AMA スーパークロス ラウンド2 フェニックス AZ レースレポートモトクロス
- スズキ GSX-R1000 – 調教された猛獣試乗インプレ・レビュー

この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!
















