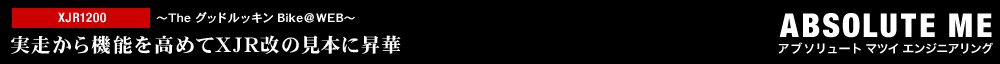
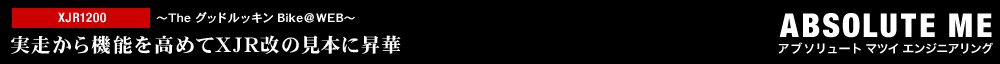

ヤマハ XJR1200
掲載日:2011年08月17日 プロが造るカスタム
スタンダードが持つ長所を伸ばし
さらに突き詰めるチューニングを行う
バイクのモデルチェンジは、カラーリングだけではない。メーカー自身が時代に合わせた改良を行ったり、さらにユーティリティを高めるような改良を行うケースも多い。ヤマハXJR1200/1300は後者の見本のような1台で、2006年末のFI化以前は、モデルチェンジごとに車体各部の軽量化や過渡特性の見直しといった進化を多く施されてきた。
そのXJRの中でも、2005年頃に完成、その後仕上がりのいいXJRカスタムの見本としてたびたび各所で挙げられてきたのが、この'98年型XJR1200(いわゆる後期型1200)だ。オーナーの松井さんはアブソリュート・マツイ・エンジニアリングを主宰。当時4輪のカスタムを15年超に渡って手がけ、途中から2輪のカスタムも行うようになり、ストリートカスタムからレースサポートまで幅広く手がけていた。
松井さん自身も乗っては改良を繰り返しでXJR1200/1300系のノウハウを蓄積した。たとえば外観の特徴でもあるハーフカウルは、1996-1998年にラインナップされていたXJR1200Rのもの。これはオートポリスの1km近いストレートでライダーへの風圧が気になって、ネイキッドのXJR1200にフレームマウントのためのステーを新規溶接している。
普通ならベース自体をXJR1200Rに、としそうだが、加工を行うことでネイキッドベースに各部を仕立てる上でのノウハウも蓄積できる。また、ツアラー的な1200Rに対して、運動性をスポイルしないようになどの付帯条件を付けることで、スポーツ方向の位置決めも行えた。
撮影時にはワイズギヤ扱いのSOQI(当時)製倒立フォーク、TZ250用φ185mm小径リヤディスクという構成だった足まわりは、撮影後にオーリンズ製φ43mm正立フォーク+ワンオフステム、同じくTZ用ながらやや大径化したφ210mmディスクなどへと変更。ここでオーリンズのXJR用フォークは'00年以降対応製品のため、アクスル径を合わせるためにカラーやキャリパーサポートもワンオフして対応している。
このフォーク変更の効果は絶大で、作動性が良く、路面からの情報量が確実に増えたとのこと。また、ステンレスEX+カーボンシェルサイレンサーだったマフラーも、後にテーパー構造のエキパイを採用したチタンEX+カーボンシェルタイプに進化している。XJRカスタムのひとつの到達点とも言えるこの車両、撮影後5年を経た今でも、各部の仕様やまとまりは十分に見習える1台だ。
- 【前の記事へ】

カワサキ ZRX1200R - 【次の記事へ】

ホンダ CB1100R
こちらの記事もおすすめです
この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!


















