ロードライダーインプレッション~ストリートファイターS / ZRX1200 DAEG ~
掲載日:2010年01月06日 特集記事
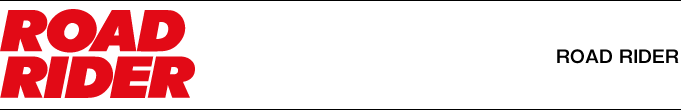
記事提供/2009年7月1日発行 月刊ロードライダー 7月号
■Report/Toshihiro WAKAYAMA ■Photo/Toshihiro WAKAYAMA/DUCATI
■ドゥカテイ ストリートファイター/Sの問合先/ドゥカティジャパン

ドゥカテイ ストリートファイターS
スーパーバイク1098を基本とするハイパーネイキッド、ストリートファイターが登場。
走りも1098直系を思わせ、ネイキッドスタイルで乗るエキサイティングさに満ちていた。
スーパーバイク直径の鮮烈ハイパーネイキッド
ストリートファイター? トラックファイターかも
まったく、ドゥカティには困ったものである。“ストリートファイター”というネーミングのことである。
ストリートファイターというのは、'70年代のカフェレーサーブームのときに使われ始めたらしいが、ここ10年ほどは究極化するスーパースポーツに対するアンチテーゼの意味合いもあるのだろうか、ハイパーネイキッドやモタードなど、サーキットではなくストリートでスポーツ性を発揮できるモデルのキャラクターを表す言葉として定着している。
実際、僕自身も「こいつはストリートファイターだ!」などと、誌面で多用してきた。だのに、その一般名詞を固有名詞にされてしまったのだ。もう、これから先はその言葉を使いにくくなるではないか。大切なボキャブラリーのひとつを失ったことが、困ったというわけである。
 それはともかく、このネーミングは、究極のストリートファイターであるとの思い入れと自信の表れなのであろう。何しろ、こいつはドゥカのスーパーバイク1098のネイキッド版みたいなものである。エンジンも車体も1098がベースで、最高出力は5ps低いものの155psもあって、車重は10kgも軽く、このSだと167kg。最新の1198と比べても2kg軽量なのだ。走りの凄さは言わずもがな、である。
それはともかく、このネーミングは、究極のストリートファイターであるとの思い入れと自信の表れなのであろう。何しろ、こいつはドゥカのスーパーバイク1098のネイキッド版みたいなものである。エンジンも車体も1098がベースで、最高出力は5ps低いものの155psもあって、車重は10kgも軽く、このSだと167kg。最新の1198と比べても2kg軽量なのだ。走りの凄さは言わずもがな、である。
だったらネーミングも“ハイパーモンスター”で良かったのにと思うが、それも従来からのモンスターとは別物で、新ジャンルを切り開いたというこだわりに違いない。
もちろん、こいつは1098から外装を外しただけのシロモノではない。プロジェクトリーダーのジュリオ・マラゴーリによると、開発で最も苦労させられたのは、補機類の設置レイアウトであったという。確かに、1098だったらバッテリーや電装品類をエンジンの周囲に置いて、カウリングでカバーすればいいが、ネイキッドではそうもいかない。
また、車体ディメンションやエンジン特性もネイキッド向きにアレンジされているのだが、それは当たり前の作り込みであって、さして苦労もなかったという。それでも、調教ぶりは見事である。
1098にアップハンドルを装着しただけでは、起きた上体が受ける加速Gや風圧のため、フロントが軽くなって加速時や高速走行時に車体が安定しないし、トルクの盛り上がりでフロントが舞い上がってしまいかねない。そこでホイールベースを45mm伸ばし、キャスター角を1.1度寝かすとともに、エンジン特性も全域でスムーズかつリニアに立ち上がる特性としているのだ。
そんなストリートファイターは、アップハンドルのネイキッドバイクに乗っているのに、それが1098であるかのような錯覚に陥らせる。いや、1098のようなのに、'70年代までのネイキッドスーパーバイクを操っている気分になると言ったほうが適当だろうか。ともかく、1098の世界をネイキッドスタイルで再現できるよう、こいつは作り込まれているのである。
 ……と、ここまで書けば、このストリートファイターの熱いキャラクターと魅力も分かってもらえたと思うが、裏を返せば、それだけ1098に勝るとも劣らないぐらいに、ライダーに求められるものも高度であるということである。ネイキッドモデルだからと、気安く接すると、マシンからしっぺ返しを喰らうことになりかねないのだ。
……と、ここまで書けば、このストリートファイターの熱いキャラクターと魅力も分かってもらえたと思うが、裏を返せば、それだけ1098に勝るとも劣らないぐらいに、ライダーに求められるものも高度であるということである。ネイキッドモデルだからと、気安く接すると、マシンからしっぺ返しを喰らうことになりかねないのだ。
特に、僕も乗り始めに感じたことなのだが、マシンはコーナーでダイナミックな荷重コントロールで曲げてやることを要求してくる。
ややソフトなフロントフォークと、1098譲りの強力なフロントブレーキに振り回され、ギクシャクしていてはダメで、フロントにかかった減速Gを逃がすことなく、ターンインさせ、さらにフルバンクに達したときはスロットルを開いてリヤに荷重を移している。そうなると、固めに感じたリヤもしっかり応えてくれるようになる。言ってみれば、スーパーバイクと同じである。
だったら、ネーミングもストリートファイターじゃなく、“トラックファイター”でも良かったんじゃないだろうか……。そう思わせてくれるほど、こいつはエキサイティングなマシンだったのである。
基本こそ1098だが、
すべてを最適化
ドゥカティ・ストリートファイター Detail Check!
こちらの記事もおすすめです
- カワサキ ZRX1200DAEG – ZRXのDNAは不変試乗インプレ・レビュー

- カワサキ ZRX1200 DAEG – まさに日々を共にすごしていく相棒試乗インプレ・レビュー

- カワサキ ZRX1200 ダエグ – スポーツ指向ビッグネイキッドの最右翼試乗インプレ・レビュー

- 【Page2】Wheelie ZRX1200 DAEG・試乗インプレ特集記事
- ドゥカティ GT1000 – スポーツ性の高い装備と185kgの乾燥重量が魅力試乗インプレ・レビュー

- ロードライダーインプレッション~カワサキZRX DAEG/1200/1100~特集記事

- しゃぼん玉 ZRX1200DAEG(カワサキ ZRX1200DAEG)プロが造るカスタム

- 怒涛の最新カスタム試乗「ゼファー1100・ZRX1200DAEG」特集記事

この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!
























