【Page2】YZとの差別化が進んだアーリーWR-F
掲載日:2010年07月14日 特集記事 › WR-Fの軌跡
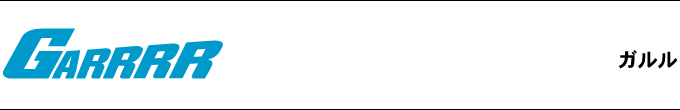
2010年3月6日発行 月刊ガルル No.288より記事提供
YZとの差別化が進んだアーリーWR-F
WR-Fの歴史を振り返ったとき、大きな節目といえるのがセルスターターの存在だ。モトクロッサーから派生したWR400Fには、キックスターターしかなかった。しかしトレールモデルのTT250Rにいち早くセルを搭載したヤマハは、エンデューロにもセルスターターの必要性を感じていたのだろう。ここではセルを掲載する前の2002年モデルまでを前期と区切って紹介していく

カテゴリー分けができない。それがYZ400F、WR400Fを最初に目にした周囲の印象であった。それまでは2ストローク250や125が大半を占めていたレースにおいて、4ストロークなら250までは2ストの125と同クラス、といったエシジンの形式と排気量で区分けされていた。
オンロードモデルで400ccはポピュラー。しかし国内のオフロードコンペティションにおいては、毎年のように新車がデビューしていた時代であったにもかかわらず、WR400Fと比較するマシンがなかった。
YZ/WR400Fは92.0mm×60.1mmというショートストロークゃ、12.5という高い圧縮比、当時としては驚くほど薄い鍛造ピストンなどによって、エンジンのレスポンスは従来の4ストを凌駕していた。加えて4スト特有の広いパワーバンドによってトラクションも良好。
「それまでの常識は捨て、エンジンから一度白紙にして考えました。より速いコーナソングを実現するためのトラクションを得られるマシンを。これを突き詰めたらYZ400Fになったんです」という話を当時の開発者の方から聞いたことがある。
2スト250は速い。だが扱いきれるのは限られたライダーだけであった。
2001年には、WR250Fが登場。ヤマハがFZ750(1985年)以来培ってきたDOHC5バルブを400同様に搭載。多くのオフロードライダーが250Fにスイッチした。このときすでに、珍しい4ストのレーサーという印象は払拭され、WR-Fは勝つためのマシンとしてトップライダーからも注目を集める存在となっていた。
399ccのDOHC5バルブ単気筒は47.5馬力を発揮。ファンライドマシンとして人気を集めていたXR400Rの30馬力を大きく上回っていた。乾燥重量は122.5kg。フューエルタンクは12l。4ストとしては十分な容量が確保されていた。多くのスペックで従来の4ストを上回っていたが、それでも2スト250との差はあり、翌2000年にモトクロッサーのYZは426ccへとボアアップ。このころすでに250Fの登場が期待される。
YZに続き、WRにも250Fが登場。77.0×53.6mmのボア×ストロークは1万500回転で38.2馬力を発揮。トルクも2.65kgf-m/9000回転とデビューから十分過ぎるスペックを持っていた。乾燥重量はなんと102kgと、モトクロッサー並みに軽快なジャンプもこなす。
WR-Fの可能性が試された時代
| WR400Fが産声を上げたとき WR400Fがデビューしたころ、日本のエンデューロはまだまだ2スト全盛。多かったのはスズキのRMX250やKDXシリーズだった。特にRMXはモトクロッサーのRM譲りのパワフルなエンジンと軽い車体が人気で、コースはチャンピオンイエローに染まってい た。WR400Fのブルーは少なく、目立っていた。 | ライトウェイトラリーとして 長い航続距離を求められるラリーにとって、4ストのニューマシンには期待がかかった。写真はビッグタンクを装着したWR400F。走行風を防ぐフェアリングや視認性のよいストップランプなども装着。WR-Fの活躍の場はエンデューロだけでなく、海外ラリーへも広がっていった。 | 新しいデュアルパーパスとして 写真は1999年に開催されたアジア3DAYSエンデューロでのワンカット。ライダーは内山裕太郎選手で、いち早くWR-Fに乗りはじめたひとり。トレールバイクに近い存在であったWR-Fは、さまざまなシーンで酷使され、耐久性を上げていった。 |
- Page1HISTORY of 5Valves Enduro WR-Fの軌跡
- Page2YZとの差別化が進んだアーリーWR-F
- Page3セル付きになり不動の地位に
- Page4YZとの決別
- Page5ライバルたちとWR-F
- 【前の記事へ】
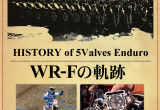
WR-Fの軌跡 ~5バルブエンデューロの歴史~ - 【次の記事へ】

【Page4】YZとの決別
こちらの記事もおすすめです
この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!























