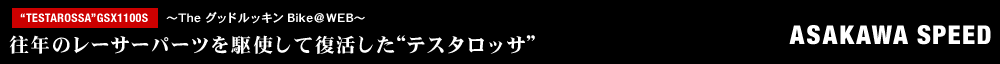
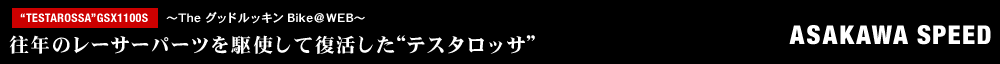

スズキ “TESTAROSSA” GSX1100S
掲載日:2010年11月29日 プロが造るカスタム
当時の本物を知るからこそ
作り得た、あるべきスタイル
「レーシングパーツを使ってカスタムする」。これをテーマにした、あるいは知らず知らずにそうなったものも含めて、そうしたカスタムバイクはじつのところ、かなりの数に上る。市販状態で足りないところ、好みの形や性能にしたいところを変えていきたくてパーツや構成、あるいは構造を変えていくのがカスタムなのだが、周知の通り、そうしたパーツがないケースもある。その場合にクローズアップされるのが、レーシングパーツだ。
例えばカスタムバイクでの使用率が高いケーヒンFCRやミクニTMRといったキャブレターも、本来はレーシングパーツだ。本体の前後長を短く取ったフラットバルブ、動きを滑らかにするベアリング採用、加速ポンプやハイパーノズルなどの特殊装備、ファンネル仕様など、レスポンスやパワーを耐久性や万能性よりも優先した構造はもちろん市販車用修復パーツとは異なるものだ。今あるアフターパーツもあまりにも一般化したがゆえにこうしたことが忘れられがちだが、レーシングパーツとしての認識で、正しいメンテナンスやセッティングを行う必要がある。
そしてもうひとつの流れとして、著名なレーシングマシンに実際に使われたパーツを取り込むというものがある。これはその車両のレプリカを作るならまず考えられる手法だし、パーツの組み合わせによってできあがる全体像がきれいであるとか、機能も、少なくともその車両が走ったときの最先端に近いところにあったわけで、そこに注目して使うこともある。
このカタナは、1980年代初頭にヨシムラが走らせた“ヨシムラ・テスタロッサ”(Testarossa。イタリア語で“赤い頭”という意味で、今ならヨシムラがキャブのトップカバーを赤の縮み塗装仕上げしていることとつなげられそうだ)を'90年代半ばに公道仕様として蘇らせたもの。“往年のスズキワークス/ヨシムラ製部品を使いつつ、今までにないレーシーでクラシカルなバイクを作る”というコンセプトの元に、アサカワスピードが復活させたのである。アサカワスピード代表の浅川邦夫さんは当時ヨシムラに在籍し、実際にこんなレーサーを作っていた経験があるから、まさに復活という言葉にふさわしい正真正銘の本物だ。
実際に各部に使われるパーツも本物だ。例えばシングルシートカウルは、台風に見舞われた'82年の鈴鹿8時間耐久レースで、デビッド・アルダナが乗ってストレートで転倒したテスタロッサ1000R(ハーフカウル仕様でピンク×白の伊太利屋カラー)に装着されていたものだし、独自のポート/燃焼室加工が行われたシリンダーヘッドも当時のレース用そのもの。さらに言うと、ブレーキパーツは8耐や世界耐久用にスズキが製作したXR(XRははスズキファクトリーレーサーのコードネーム)パーツだ。
そんなお宝パーツを丹念にレストアし、カタナではないカタナとして生まれたのがこのテスタロッサ。ダブルクレードルフレームこそストックだが、きちんと動く前後サスペンションや適切なホイール&タイヤ選択のおかげで、今の公道も快適かつ素直に走ることができる。
古い(新しいものであっても、冒頭のような注意が必要だ)レーサーパーツは時としてトラブルの原因になるし、誰もが手を出せるものではないけれど、このテスタロッサに限っては、心配は一切無用。こんな時を超えたパッケージが存在すること自体、夢のよう。カスタムのあるべきひとつの形と言ってよさそうだ。
- 【前の記事へ】

カワサキ Z1000J - 【次の記事へ】

ホンダ CBX(1000)
こちらの記事もおすすめです
この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!


















