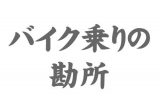環状交差点
掲載日:2014年09月08日 タメになるショートコラム集 › バイク乗りの勘所
Text/Nobuya YOSHIMURA
2014年9月1日施行の改正道路交通法により、本格的に環状交差点の運用が始まった。今さら…の感、なきにしもあらずだが、わが国の道路行政・交通規制における画期的な取り組みとして、大いに歓迎したい。利用者(通行車両の運転者)から見た環状交差点の通行上の注意は、警察庁や各都道府県警察が、今まさに広報・啓蒙運動を展開中であり、警察庁のホームページには環状交差点の走り方をわかりやすくまとめたPDFファイルが用意されている。
環道の進行方向は右回り(上から見て時計回り)で、環道を走る車両(先に入った車両)が優先し、環道から外に出るときは左の方向指示器で合図をするということを覚えておけば、慣れていなくても大丈夫。要するに、左折であれ直進であれ右折であれ転回であれ、左に曲がって環道に入り、左に曲がって環道から出るのである。これがなぜ安全につながるのかは、wikipediaの該当ページの“安全性”の項に、交錯点を比較した詳しい記述がある。
ところで、なぜ最初に“画期的”と書いたのか、それには2つの理由がある。ひとつは、信号機による交通整理とは異なり、運転者の判断に負うところが大きいこと。もうひとつは、交通の流れを“止める”よりも“流す”効果が高いからである。環状交差点では、漫然と信号(だけ)を頼りに運転するのではなく、まわりの状況を見て、交差点に進入してよいかどうかを個々の運転者が判断するわけだから、従来とは対極的な施策と言っても過言ではない。
都市部だけでなく、交通量の少ない郊外の信号機つき交差点の多くが環状交差点になれば、ムダな信号待ちを強いられることなく、快適なツーリングが楽しめるのではないかという期待もある。今後、全国各地に環状交差点が増えることを願いたい。なお、環状交差点を意味する英語はroundaboutであり、ランダバウトならともかく、ラウンドアバウトという呼び方は耳ざわりなので、本コラムでは道交法の条文に従い、環状交差点と表記した。
- 【前の記事へ】

雨のツーリング - 【次の記事へ】

リターンについて思うこと
こちらの記事もおすすめです
この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!