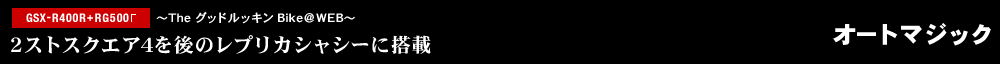
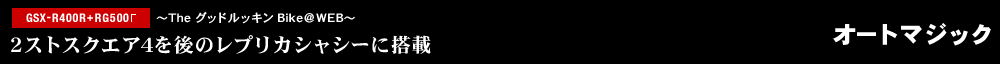

スズキ GSX-R400R+RG500Γ
掲載日:2011年04月06日 プロが造るカスタム
DFC登場の萌芽さえも感じさせる
究極系ハイブリッド・カスタム
流用足まわり改を中心にカスタムブーム初期から頭角を現し、純正流用カスタムという手法を確立。リヤホイールのワイド化を数多く行ううちにチェーンラインの適正化を図る必要からフロントスプロケットの外オフセットで対策。そのために作られたオフセット・フロントスプロケットなど、そうした作業から生まれたオリジナルパーツも用意する、オートマジック。今回紹介するのは、一見'91年型GSX-R400Rのカスタム。だが、車名は“GSX-R400R+RG500Γ”。
これが何を意味しているかというと、その名の通り4スト400レプリカ、GSX-R400Rのアルミダブルクレードルフレームに'87年のRG500Γ用スクエアフォア・2ストロークエンジンを合体させたもの。この中には、後にオートマジックが展開するDFC=デュアルフレーム・コンバインドシャシー(Dual Frame Combined Chassis)に通じる要素も垣間見えている。
元々はRG500Γに対して「エンジンは気に入ってるけど、スタイル(アルミダブルクレードルだが、GSX-R400Rよりひと世代前の細身の角型パイプ+鋳造ヘッドを使っていた)は……」と考えたオーナーが、理想のスタイルとして掲げたGSX-R400Rの外装を装着できないか、とオートマジック・荒木さんに相談したことがスタート。同時に足まわりの変更も伝えると、荒木さんは「Γベースなら、ディメンションそのものを現行車(後のモデル)に近づけたほうが性能を発揮できる」と、逆にGSX-R400Rの車体をベースにしてカスタム化することを提案した。
当然、作業の中心、かつ1番のキモになったのはエンジンの換装だ。剛性メンバーとしての効果をあまり見込まずシャシーには「お客さん」的に積まれる2ストロークエンジンを、エンジンブロックを剛体とみなす4スト車の車体に積むにはもちろんそれに応じた配慮が必要。そこでまずΓエンジン前後左右のセンターを出し、車体搭載時のフロントスプロケットとカウンターシャフトの位置を決定。続いてGSX-Rフレームのダウンチューブを切断し、同様にカットした500Γのダウンチューブの前後端を内側に送り、マウントを追加した上でGSX-Rフレームにジョイントした。
スクエア4エンジンは前側2気筒分の2本のチャンバーを右2本出しにすることで、膨張室の位置をずらして最低地上高を確保した。フレーム右後半部への干渉に対しては、スイングアームにホンダNC30(VFR400R)の片持ちタイプを使うことで対処。ただしこのスイングアームは幅の狭いΓ用エンジンに対してチェーンラインが出しにくかったため、結果的にスイングアーム側のピボット部はほぼワンオフで作り直すこととなった。
「単なる換装から飛躍して、ついハマってしまった」と荒木さんは言うが、目論み通りΓのエンジン性能にGSX-Rの車体メリット=走行面と、オーナーの望んだGSX-R外装が融合。この状態で認可も受け、同仕様の注文にも比較的容易に応えられるメリットも新たに得られた。この後しばらくして荒木さんはふたつのフレームを強固に結びつけることでベースのふたつのモデルの良さを融合するDFC発案に至るのだが、このGSX-R+Γは、その習作と言っていいだろう。
- 【前の記事へ】

カワサキ 750RS - 【次の記事へ】

カワサキ GPZ900R
こちらの記事もおすすめです
- YOSHIMURA MJN: THE GAME CHANGING CARBURETOR

- スズキ新型GSX-8T/8TT 新商品説明会 速報レポートフォトTOPICS

- 【スズキ GSX-S1000F 試乗記】これ一台ですべてをまかなえる、ある種の”アガリ”バイク試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-R600(2015) – 20年以上の進化熟成を重ねたミドルスーパースポーツ試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-S1000 – GSX-Rの走りを真に公道で楽しめる!試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-R1000 – 調教された猛獣試乗インプレ・レビュー

- 【スズキ GSX-S1000GX 試乗記】ド根性スタイルには疲れた。でも刺激欲は枯れてない。そんなアナタへ試乗インプレ・レビュー

- スズキ GSX-S1000F ABS – 甲乙が付けられない2台のGSX-S試乗インプレ・レビュー

この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!










