
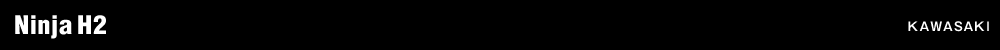

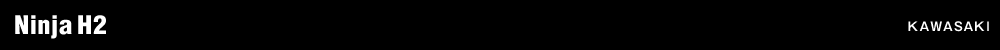
掲載日:2015年06月04日 試乗インプレ・レビュー
レポート/和歌山 利宏 写真/吉見 雅幸 記事提供/ロードライダー編集部
※この記事はカスタムNo.1マガジン『ロードライダー』の人気企画『New Model Impression』を再編集したものです
今回のNinja H2の試乗に当たって僕は、怖いもの見たさみたいな体験を期待していたかもしれない。
そりゃ、そうである。最高出力200psは自然吸気のスーパースポーツが達成しているとは言え、各種電子制御装置の助けを借りずに使いこなせるものではない。そればかりか、スーパーチャージャーによって新気が詰め込まれ、トルクが全域でアップ、それも低中回転域で格段に強化されているに違いない。それに、過給によるトルクアップは、凶暴かも知れず、不安も付きまとう。
とは言え、日本のバイクメーカーが多くのライダーが楽しめるように作ったバイクが、手に負えなくて危険なものであるわけはない。と、自分を落ち着かせようともしていた。
そして乗ったH2。怖いもの見たさの好奇心は満たされ、それでいて手に負えないシロモノではないことも分かった。でも、本当に印象的だったのは、怒涛の動力性能とか、それが調教されているといったことだけでない。それらが絡み合い、これまでのどのバイクにもないスポーツ性が具現化されていたことである。

跨るとライディングポジションは快適指向のスーパースポーツといったところ。実際、車格はスーパースポーツをひと回り大きくした程度で足着き性も悪くなく、普通に乗れそうな雰囲気だ。が、そこそこ重量感があるし、タンク上面は高めで、それなりのボリュームを感じさせる。
クラッチを繋ぎ走り出すと、すぐに緊張感は吹っ飛ぶ。スロットル全閉ではやや頼りなさを感じさせても、ほんの少しでもスロットルを開けると、スーパーチャージャーの駆動も始まるのか、いつでもほしいトルクを取り出せるという安心感に満たされる。それも唐突さはなくスムーズで、街乗りも普通にこなせるはずだ。
コーナーでは最初、燃料タンクの下、股の間あたりに、普通のバイクにはない重量物を感じる。おそらく、スーパーチャージャー自体の重さなのだろう。だから、純粋なスーパースポーツのような身軽さはない。

でも、それは一般的なスーパースポーツを基準に考えるからであって、この重量バランスなりの身のこなしを心掛ければ、至って素直で、優雅なリズムでタイトなコーナーをこなしていくことができる。実に気持ち良く走れるのである。
そしてコーナーでは、スロットルでマシンを操作しやすいことに感心させられる。スロットルワークがうまくなった気がするほどで、クリップで加速に移る手前から、ジワリとスロットルを開け始めるという4スト本来のリズムに自然と導かれる。脱出加速に入った辺りで、スーパーチャージャーのショックが感じられるが、トラクションの変化はあくまでもリニアで忠実である。
一般的なスーパースポーツなら1速で回る低速コーナーを、1速でスムーズなのはもちろん、3速でもこなせるほど低速トルクが豊かだ。しかも、トルクカーブは驚くほどリニアでフラットに吹き上がり、スロットルワークに対しても、リニアにトルクが湧き出てくる。

だから、右手でほしいトルクをほしいだけ取り出すことができる。高速コーナーにおいて、トルクカーブに乗ってスリリングに加速していくのではなく、狙ったラインに合わせてほしいトルクカーブを自分で作り出せると言っていい。速度を落として向きを変え、一気に怒涛の加速をすることもでき、格段に走りの自由度が高まっているのだ。
トラスフレームによる車体も、この自由度を高次元化している。適度にしなりながらもヨレを感じさせることはない。高剛性な車体が高い安定性を維持して向き変えに労力を要求するのではなく、しなりを生かして状態を変化させることができるし、要らぬ緊張感も伴なわない。
これは、一般的なスーパースポーツとは異次元の世界である。マシンに自身を合わせるのではなく、自身が走りを創造していけるという意味で、スポーツ性が高いと言える。

既存モデルにない走りを求めてH2は生まれ、画期的な構成のモデルとなった。従来にない高性能を得るため、水冷998cc並列4気筒エンジンにはスーパーチャージャーを搭載。またフレームは外乱をいなし、誰もが超高性能を生かせるようにと、トラスフレームの採用となった








愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!