
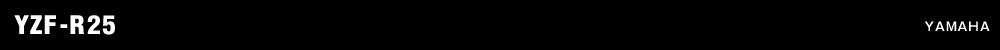

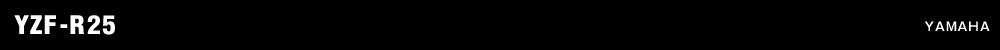
掲載日:2014年12月11日 試乗インプレ・レビュー
レポート/和歌山 利宏 写真/徳永 茂 記事提供/ロードライダー編集部
※この記事はカスタムNo.1マガジン『ロードライダー』の人気企画『New Model Impression』を再編集したものです
多くのライダーが登場を待ち焦がれてきたYZF-R25が、ついに市販となった。早速の試乗となった場所は伊豆サイクルスポーツセンターの5kmコース。そもそもは自転車用で、言ってみれば、ここは対向車の来ないワインディングロード風といったところ。とにかく、R25でそこを走って、最高に楽しめたのである。
では、どうして、そんな楽しかったのか?それは何より、楽しみが普段の生活の空気の中にあるということではないだろうか。
高度化したリッタークラスのスーパースポーツのように、サーキットという限られた場所で、歯を食い縛り頑張ってこそ、本領が発揮できるというものではなく、生活圏の中で、ちょっとその気になれば楽しめる。しかも、その楽しさの質はスーパースポーツと何ら変わらない。

ライディングポジションはこの手のバイクとしてはアップライトで、足着き性は悪くないし、車重が軽く、ハンドル切れ角は一般的なネイキッドモデル並みにある。だから、気負わずに使えて、実用性もたっぷりだ。そして、普通の軽量ストリートバイクのようにさりげなく向きを変え、コーナリングすることもできる。
でも、これだけのことだったら、単なる街乗りバイクといったところだろう。R25の場合は、もっとスポーツしようという気にさせてくれる。そして、いざそうなると今日的なスーパースポーツよろしくダイナミックな荷重移動にも応えてくれる。
しかも、荷重コントロールが的確であるほどに、しっかり曲がるし、接地感も伝わり、マシンを自分のコントロール下に置くことができる。自分のライディングいかんに、しっかりマシンが反応してくれるのだ。だから一層楽しくなる。これぞまさにスポーツなのである。

前後サスは豊かに姿勢変化するようにセッティングされているが、スポーツするためにもその姿勢変化を生かし、荷重コントロールをシンクロさせることが大切のようだ。
動力性能、ブレーキ、サスペンションなどマシンの全ては、一線級のスーパースポーツのように高度化し洗練されているわけじゃない。でも、全てがそれぞれの性能を生かし切れる範疇にあって、バランス良くまとまっている。だからこそ、心底マシンコントロールを堪能することもできるのかもしれない。

さて、動力性能に関してであるが、これも特性は絶妙な設定だ。最高出力の36psは、このクラスのロードスポーツとしてダントツの高さで、合法的に公道を走り、またワインディングを走るうえで、物足りなさを感じたり、かったるさにストレスを強いられることもないだろう。
それでいて、もっと走れとばかり、性能を目一杯引き出す面白さがある。7,000rpm以上を使えば、コーナーの立ち上がりでトルクカーブに載せられて、トルクピーク10,000rpmに達する少し手前から、一気にエンジンの様子が一変。ピーク域に突入し、レッドゾーン14,000rpmの手前、13,000rpm超辺りまで多用すれば、それはもうエキサイティングのひと言。
かつての2ストクォーターを思い出させる爽快感があって、いい意味でピーキーでもある。久々にタコメーターをしっかり見てライディングする面白さを味わった気分だ。使いきれないパワーの一部だけを取り出しながら走るよりも、こちらのほうがはるかにスポーツである。
中速域のトルクは、ライバル車には劣るかもしれない。でも、公道でのクルージングにことは欠かないだろうし、メリハリよく走りたいなら、頻繁にシフトチェンジすれば、後輪駆動力を補うことができよう。
そもそもクォータースポーツは、ロードスポーツとしてベーシックな存在だったはず。単なるビギナー向けのお手軽モデルでも廉価版でもなく、走り屋も含め多くの人が楽しめるものだったのだ。その意味でR25は、久々に帰ってきたリアルクォーターだと言っていい。


YZF-R25(アール・ツーファイブ)は、「毎日乗れるスーパーバイク」をコンセプトとして、クラス最高の出力とRシリーズを継承するデザインを奢り、スーパースポーツを具現化した。車重はガソリン満タンで166kgと軽く、シート高は780mm。その生産はインドネシアで行われる








愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!