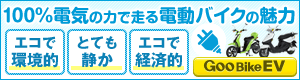第8回 電動バイク生活のはじめ方
掲載日:2012年01月16日 電動バイク生活
Text & Photo / GooBike


電動バイクはガソリンがいらないエコな乗り物です。EV(Electric Vehicle)とも呼ばれるこの新世代のモビリティは、現在各メーカーが様々な車両を販売しています。とはいえ、これまではガソリンエンジン車を軸として考えていた免許区分や排気量区分は、電動バイクではどうなるのでしょう? 今回はそうした基礎知識をまとめてみました。
Point 1
EVと免許のハナシ
| 公道で乗る以上、もちろん電動バイクにも免許は必要です。道路交通法による今までの2輪免許の考え方では、排気量の大きさで必要な免許が区分けされていますが、電動バイクはモーターのため排気量がありません。そのかわり、モーターが発生させることのできる最大出力の大きさ(kw)によって必要な免許を分けています。例えば現在一番車両の多い原付枠では、モーターの出力が0.6kw未満と決められています。
ただ、カテゴリーが新しく法整備が追いついていないため、125cc以上となる電動バイクは現状の区分けではすべて中型免許で乗ることができるのです。詳細は表の通りですが、これらの出力はどのメーカーの車両諸元表に明記されているのできちんとチェックしてみましょう。
|
| 原付2種のマーク 原付2種にはナンバーの色以外に、原付車両にはない違いがあります。それが車体前後の認識票です。車体前方の先端には黒線で囲まれた白いシール、車体後方には三角マークが付けられています。 |
| 電動バイクを運転可能な免許の種類 | 乗れる車両 | ||
| ~50cc(0.6kW) | 50cc(0.6kW)超~125cc(1.0kW) | 125cc(1.0kW)超~ | |
| 原付 | ○ | × | × |
| 普通自動2輪(AT小型限定、小型限定) | ○ | ○ | × |
| 普通自動2輪(AT限定) | ○ | ○ | ○ |
| ※上記の免許は全て16歳から取得可能 | |||
| ※普通自動車免許には、原付免許が付帯しています。 | |||
Point 2
免許区分と道路交通法のハナシ
電動バイクにもきとんとした免許区分があることは分かりましたね? では実際に公道を走る上で注意しなければならない道路交通法にも触れておきましょう。ただ、『車両が電動バイクだから道交法が違う』ということはなく、あくまで走らせる車両が原付なのか原付2種なのか、それとも普通2輪なのか、それによって道交法は変わってくるのです。
一番基本的なものとして知られているのは、表にある通り一般道での法定最高速度の違いと、二人乗りの可否、そして大きな交差点などでの二段階右折でしょう。免許区分の中で一番下位にあたる原付免許では、これらに制限がかけられています。また、表以外にもオーバー・アンダーパスの通行禁止、法定速度が30km/h以上に設定されたバイパス等での走行が禁止されていることもあります。
原付免許はそうした意味では縛りの多い免許となりますが、そこに不満を感じたら、上位免許を取得し、原付2種以上の車両に乗るしかありません。注意して欲しいのは、道交法は走らせる車両によってルールが決まっている、ということ。大型二輪免許を持っているからといって原付でも自由に走れる、ということはありません。乗っている車両に沿ったルールで走る必要があるのです。
|
| 法定最高速度(一般道) | 高速道路 | 二段階右折 | 二人乗り |
| 原動機付自転車1種 | 30km/h | × | 必要 | × |
| 原動機付自転車2種 | 60km/h | × | 不要 | ○ |
| 軽2輪 | 60km/h | ○ | 不要 | ○ |
| 大きな交差点では二段階右折 片側2車線以上の大きな交差点では、原付は右折できません。写真のように、一旦交差する道路の先頭に出て、その道路信号が青になってから発進します。これが二段階右折です。交差点手前の二段階右折標識をしっかり確認しましょう。 |
| オーバーパス、アンダーパスの走行禁止 主に都市部に多いのですが、アンダーパス、オーバーパスと呼ばれるトンネルや陸橋などで原付の走行が禁止されている場合もあります。原付車両で街中を走る際には、常に道路標識を気にしながら走りましょう。 |
Point 3
免許取得方法のハナシ
| さて、電動バイクに乗る上で必要な免許や道交法について学んだところで、実際に運転免許を取得する方法について簡単に説明します。原付免許は、全国の自治体にある運転免許試験場で一発試験を受けて取得します。それ以外の方法では、普通自動車免許を取得することで、自動的に原付免許を取得したとみなされます。
それ以上の小型2輪免許、普通自動2輪などの上位免許については、試験場での一発試験のほか、教習所での学科技能試験をクリアする必要があります。表の中に免許取得に必要な金額をまとめてみました。教習所の料金は教習所ごとにことなるのでその都度確認してみましょう。
|
|
|
| 原付 | 普通二輪免許(小型限定、AT小型限定、AT限定を含む) | |
| 取得方法 | 運転免許試験場での一発試験のみ | ・運転免許試験場で一発試験 | ・教習所を卒業しで技能試験免除の資格を得る |
| 試験で必要なもの | ・住民票の写し(※本籍記載のものが必要) | ・住民票の写し(免許を持っていない人) | |
| 必要となる金額 | 受験料 1650円 | 受験料 3300円 | |
| 試験合格後に受ける講習料 | 教習料金 普通2輪 約10万円~約23万円 | ||
Point 4
購入後にかかるお金のハナシ
| では、実際に電動バイクを購入した後に必要となってくるお金のハナシに移りましょう。まず原則として、電動だからといって、購入後にかかる法定費用(法律で決められた税金など)が変わることはありません。あくまでその車両が原付、原付2種など、どの車両区分に属しているかの違いだけです。表のとおり、原付車両は税金や自賠責(加入が義務付けられた強制保険)の金額がとてもリーズナブルですし、原付2種までの車両であれば、自家用車を所有している場合に車の任意保険特約を利用して、お得に任意保険に入ることができるんです! (保険内容や金額は保険会社によって異なります)最近原付2種が売れている、という理由のひとつが実はこうしたコスト安だったりします。
表の中の数字が車両以外にかかる最低限必要な金額ということになります。ですから、「さぁ電動バイクを買おう!」と思った時には、車両本体価格に加えてこれらのお金が必要になる、という計算をしておきましょう。もちろん、バイク屋さんに行くと、こうした総支払額はすぐに教えてくれます。
|
| 保険証書は携帯しよう 公道走行する際に加入が義務付けられている『自動車損害賠償責任保険』、通称『自賠責』は街のバイクショップやコンビニなどでも加入できます。証書を常に携帯するのも義務なのです。 |
| これが自賠責ステッカー ナンバーの左端に貼ってあるのが自賠責ステッカー。有効期限の年号と月が記入されています。日付までは入っていないので、証書で確認しましょう。一日でも期限を過ぎると保険は無効になってしまいます! |
| 法定料金 | 所有する車両 | ||
| ~50cc(0.6kW) | 50cc(0.6kW)超~125cc(1.0kW) | 125cc(1.0kW)超~ | |
| 軽自動車税(年額・標準税額) | 1000円 | 50cc(0.6kW)超~90cc(0.8kW)=1200円 | 2400円 |
| 自賠責保険料(12ヶ月) | 6960円 | 8620円 | |
| 任意保険での | ○ | ○ | × |
| ※オートバイやクルマの任意保険に入っている場合、ファミリーバイク特約に追加して入ることで、原動機付自転車で事故にあった場合、契約しているオートバイもしくはクルマととほぼ同様の補償がうけられるというもの。任意保険を既に契約しているなら、原動機付自転車単体で保険に入るよりも、格安で保険を契約できる。 | |||
- 【前の記事へ】

オーヴァー・クリエイティブ JEVO 試乗インプレッション - 【次の記事へ】

第9回 電動バイクのモーターについて知ろう!
こちらの記事もおすすめです
- 話題沸騰の高性能アクスルシャフト P.E.O. ZERO POINT SHAFT。その、パフォーマンスの秘密に迫る(動画あり)特集記事&最新情報

- アクスルシャフトが走りを変えるゼロポイントシャフトの実力検証

- ピアジオ MP3 ハイブリッド 300ie – 3ホイーラーMP3のパワーユニットをハイブリッド化試乗インプレ・レビュー

- ガスガス 2015年エンデューロモデル試乗インプレ・レビュー

- 第11回 電動バイク用語の基礎知識電動バイク生活

- 第10回 バッテリーについて電動バイク生活

- 第9回 電動バイクのモーターについて知ろう!電動バイク生活

- 【ホンダ CRF450L】指定スケジュールに沿ったメンテナンスでポテンシャルをキープ! 密着 初回&1000km点検フォトTOPICS

この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!