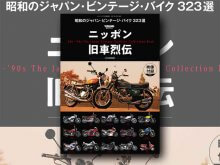【ヤマハ YZF-R3 試乗記】ヤマハらしい硬派でスポーティな仕上がりが魅力
掲載日:2025年08月18日 試乗インプレ・レビュー
取材・文・写真/小松 男

YAMAHA YZF-R3
すでに10年選手となったR3
作りの良さで変わらぬ人気を保つ
今回取り上げるYZF-R3の初代モデルと、ピストンの内径が一回り小さいR25が登場したのは2014年のことだ。MotoGPのレジェンドライダーであるバレンティーノ・ロッシがヤマハワークスチームに復帰したころで、その影響もあり出るや否や爆発的なヒットモデルとなった。

当時すでにクオータークラスのフルカウルロードスポーツモデルは他社からも出揃いマーケットは活況であった。ほとんどのモデルが上位機種として400ccクラスのモデルを用意していたのだが、YZF-R3とR25の関係性がそれらと異なる点は、ライバルたちが250と400をほぼ別物としてリリースしていたのに対し、YZF-R3とR25はフレーム、足回り、ベースエンジンなどを共通としていたところだろう。
実際、触手を伸ばすユーザーがどちらを選ぶか困惑してしまうという噂もしばしば耳にしたものだが、実際に乗ってみると、トルク感や出力特性など明確な違いが感じられるものだった。そんなYZF-R3/R25は幾度かモデルチェンジが図られ、2025モデルではスタイリングのブラッシュアップ、アシスト&スリッパ―クラッチの採用、スマートフォンアプリとの連動機能など、細部に手が加えられている。
今回は普通自動二輪免許で乗ることができる最大のYZF-RであるYZF-R3をピックアップし、その内容をお伝えしていこう。
ヤマハ YZF-R3 特徴
従来モデルのオーナーはわかる
スタイリングのシャープ化

2000年代後半に差し掛かった頃のことだったが、それまですっかり身を潜めていた250ccクラスのフルカウルロードスポーツモデルに急にブームが巻き起こる。その口火を切ったのはカワサキのニンジャ250R(後のニンジャ250)で、ホンダCBR250R、スズキGSR250が続いた。

昭和生まれのライダーからすると、クオータークラスのフルカウルロードスポーツモデルといえば、レーサーレプリカ的な過激な仕様のモデルを頭の中にイメージする節があり、4ストロークのシングルやパラレルツインエンジンを搭載し(レプリカといえば2ストロークか4気筒だった)、ややパンチに欠けたニュージェレーションモデルたちに違和感を覚えなくもなかった。そのような中、沈黙を続けていたヤマハがついに、マーケットに投入したのがYZF-R25および今回紹介するYZF-R3だった。

ライバルたちがスポーティなスタイリングでありながらも乗りやすさを追求したパッケージングだったのに対して、スポーツライディングで得られる心地よさを引き上げつつ、さらに日常生活でも扱いやすくされたキャラクターとされており、まさしくヤマハが掲げた『毎日乗れるスーパーバイク』というキャッチコピーを具現化したものだった。

その後ライバルモデルたちも、スポーツ性能に磨きを掛ける方向へとシフトしていったが、YZF-R25/3のように、登場からこれまで一貫してピュアスポーツバイクとしてのキャラクターを固持しているモデルはない。
ヤマハ YZF-R3 試乗インプレッション
ライディングテクニックを見直すのに
ちょうどよいサイズとパフォーマンス

ここ一年ほどは、YZF-Rシリーズといえば、大型自動二輪免許区分となるR7や、R25/3よりも小さなR125/15に乗る機会が多く、R3に触れるのは数年ぶりのこととなった。
フロントカウル左右のヘッドライトや、中央のM字グリルなど、一目見ただけでYZF-Rシリーズだとわかるアイデンティティが確認できるが、ヘッドライトは薄めの意匠に変更された他、テールカウル周りもすっきりしたデザインとなり、全体的にシェイプアップされたかのような印象を受ける。

ただし新型と従来モデルを隣に並べて変更点を指差し確認するようなことをしなければ、スタイリングに関しては、どこがどう変更されたのかはなかなかわからないと思う。これは従来モデルオーナー的に考えると嬉しいと思える点ではなかろうか。

私は普段から大型のモデルに乗り慣れていることもあり、実車に跨ったところでサイズ感的にはコンパクトに思えてしまったものだが、もし免許取り立てで、これが始めてのバイクとなるならば、やはり大きいと感じるかもしれない。しかし車両全体のフォルムが細身なことと、車重も169kg程度なので、ビギナーや体格に自信がないライダーであってもすぐに慣れることだろう。特に2025モデルではシートと左右サイドカバーの幅が狭くなっているため、その分足つき性は向上している。
エンジンを始動し走り出すと、想像していた以上にトルクがあることが伝わってきた。R3のエンジンは排気量320ccで、その数値だけ見てしまうと、やや中途半端感は否めないのだが、R25と比べて約70cc大きいのだから、そのパフォーマンスの差は誰しもしっかりと体感できるものなのである。
低回転域ではややこもった音質に思えたエキゾーストノートは、中~高回転まで引っ張るとレーシーなサウンドを響かせる。軽くされたクラッチレバー操作感や、急激なシフトダウン時にもリアタイヤを暴れさせないスリッパークラッチなど、ちょっとしたことから、スポーツライディングをすることの楽しさを引き上げてくれる改良が加えられたことが伝わってきた。

市街地を走らせるだけでも、運動性能の高さは良く分かるが、R3の真価はワインディングロードでこそ発揮される。加速、減速、コーナーへの飛び込み、そして脱出という一連のコーナーリングの組み立てを、極めてナチュラルに行うことができるだけでなく、コーナーリングの組み立てを考えつつ走れば、その分狙ったラインをトレースできるようになる。タイヤの端までしっかり使い切る走りを楽しむことができるはずであり、それは総じてバランスが良いということの裏付けとなる。
そして実はこのキャラクターは、本格的なレーシングロードスポーツモデルのそれであり、YZF-Rシリーズは一貫してそれを貫いているのである。だからいつ走らせてもエキサイティングなのだ。
R25と比べて豊かなトルクのあるR3は、やや高めのギアを選んでもスロットル操作についてくるポテンシャルがあるが、一速落とせばよりスポーツプレジャーを得られるシーンも多い。そんな懐の深さこそ、YZF-R3の大きな魅力となっているように思える。

フロントコクピット脇には電源ソケットが装備されたほか、スマートフォン専用アプリであるY-Connectとの接続も可能になるなど、実用面の充実も図られている。
フルカウルロードスポーツモデルであってもストリートモデルの場合には緩めのライディングポジションが多くなる傾向にあって、R3は結構タイトなライディングポジションであり、ストイックな面もあると思えるが、それがスポーツライディングを求める人々への訴求力となっていると言える。
R25とR3を比べた際に、”車検があるから”とR3を諦める方も多いが、それ以上に得られる喜びが秘められていることを今一度伝えておきたい。
ヤマハ YZF-R3 詳細写真

ボア・ストローク68×44.1㎜の320cc並列2気筒エンジンは、最高出力42馬力、30Nmの最大トルクを発生する。R25とはボアが8㎜拡大されているだけでなく、圧縮比も若干下げられていることから、回転上昇フィーリングも異なる。満タン法での燃費は32km/L程度だった。

ゴールドのアウターチューブとされたφ37㎜の倒立フォークやフローティングディスクローターを採用するなどワンランク上の装備が奢られたフロント足まわり。ラジアルタイヤであるダンロップ・GPR300との相性も良い。

左右非対称のスイングアームを採用。タイヤサイズは、フロント110/70R17、リア140/70R17。マスの集中が図られたショートサイレンサーもあり、総じてスポーティな雰囲気でまとめられている。

YZF-Rシリーズのアイデンティティをしっかりと受け継ぎつつ、2025モデルでフロントマスクはより一層精悍なイメージとされた。興味深いのはウインカーの取付位置がかなり高くなったことで、従来よりも転倒時に破損しにくいと思われる。

シート高は780㎜。ライダー側のシートとサイドカバーの幅が狭められたことにより、足つき性は向上している。テールカウルおよびパッセンジャーシート形状も変更されている。

前から後ろに向かって貫通した大胆なデザインのテールカウル。スポーティな雰囲気でまとめらていることはわかるが、パッセンジャーシートの幅から左右に飛び出しているため、乗り心地が気になるところ。

マルチファンクションタイプのメーターディスプレイ。回転計、速度計、残燃料計、水温、シフトポジションと、ライダーが求める基本インフォメーションが伝わってきやすい。スマートフォンの専用アプリとの連動も可能となった。

肉抜き加工されたトップブリッジや低めにセットされたセパレートハンドルなど、このクラスのフルカウルロードスポーツモデルの中でも俄然スポーティなコクピットとなっている。なおクラッチレバー操作は従来モデルよりも軽くなっている。

パッセンジャーシート下のユーティリティスペースは想像以上の容量が確保されていた。テスト車両では取扱説明書をはじめとした書類が収まっていたが、それを省けばETC車載器と100均ポンチョ程度は入れることができそうだ。

燃料タンク容量は14Lでレギュラーガソリン指定。カラーバリエーションは写真のブルーのほか、マットダークグレーとマットパールホワイトが用意されている。

ヒールガードもしっかりしており、スポーティなデザインを受けるステップまわり。個人的にはステップ位置は若干後方に移動するともっと乗りやすくなるだろうと思えた。なお2025モデルからスリッパークラッチを標準で装備

ロング気味に設計されたスイングアームとモノクロスタイプのリアサスペンションの相性が良く、深々としたバンクを楽しむことができる。高い運動性能を武器に、より排気量の大きなモデルでも相手をすることができる。

メーターディスプレイの左わきに新たにUSB タイプAの電源ソケットが装備された。スマートフォンなどのガジェットを使うことが一般的となった今、標準装備となるのは嬉しいことだ。
こちらの記事もおすすめです
- 2015年のMotoGPの世界を完全再現した最新ゲーム「MotoGP™15」登場

- 中野真矢も認める驚異の再現度、MotoGP™20は究極のライディングシミュレーターだ特集記事&最新情報

- 2016 MotoGP 日本グランプリ イベントレポートトピックス

- YZF-R25をYZF-R1のスタイルに一新させる才谷屋ファクトリーのカウルキット

- 【ヤマハ YZF-R125 vs ヤマハ MT-125 試乗記】独断と偏見で2車を比較!バイクブロス的ガチンコライバル対決!試乗インプレ・レビュー

- 250ccパラレルツインの兄弟車、YZF-R25とMT-25を徹底比較!!特集記事&最新情報

- 【ヤマハ YZF-R125 試乗記】フルカウルスポーツのエントリーモデルとして好適試乗インプレ・レビュー

- 2スト500cc時代のレジェンドライダーも登場‼ 「MotoGP™22」特集記事&最新情報

この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!