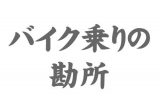オイルレベルは低いほど良い?
掲載日:2011年11月07日 タメになるショートコラム集 › バイク乗りの勘所
Text/Nobuya YOSHIMURA
タイトルの最後につけた “?” は、予防線であり、私自身のバイクのエンジンオイルに限って話をすれば “!” である。エンジンオイルは通常、クランクケース底部の容器(オイルパン)の、そのまた底からオイルポンプで汲み上げられ、エンジン各部に圧送されている。だから、冷却や劣化などといった条件を無視して極端な話をすれば、オイルポンプの吸入口よりも上までオイルが入っていれば(空気を吸わなければ)潤滑不良に陥ることはない。
オイルレベル点検窓やレベルゲージに上限と下限のマークがあり、2本の線の間に保つように指示されているのは、1本の線に合わせるのが難しいからだ。なぜなら、運転状況や気温によるわずかな粘度の変化により、エンジンを停止したときにオイルパンに戻ってくる(各部に留まる)オイルの量に違いが生じたり、車体のわずかな傾きで油面が変化したりするからだ。入っている量は同じでも、油面の高さは変化して当然なのである。
今の日本製車両で目に見えてオイルが減るのは故障である。修理するか補充しながら乗り続けるかはオーナーにお任せするとして、故障していない前提で話をすると、オイルレベルが高ければ高いほど、クラッチやクランクがオイルをかき混ぜることによって抵抗(撹拌抵抗)が増えたり、ブリーザー(通常、ホースでエアクリーナーに接続)からオイルを吹きやすくなったり、クランクケース内の空気容積が減ってポンピングロスが増えたりする。
これに対して、冷却や劣化防止のためには、オイルレベルが高い(たくさん入っている)ほうが良いが、それは、油温を下げる必要があったり劣化がヒドい場合に考えればよく、下限マークに合わせた程度では大差は生じない。良いオイルを、指定範囲内の下限に近いところまで入れ、下限マークを下まわらないようにチェックしながら使う…。これにより、出力と燃費を改善し、入れすぎによるトラブルを回避することができる。
- 【前の記事へ】

まぶしいクルマやバイクが多すぎる - 【次の記事へ】

救急車のサイレンを改良すべし
こちらの記事もおすすめです
この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!