絶版フラッグシップの誘惑 ~ホンダ CB750R(CR750) 1970~
掲載日:2010年04月21日 特集記事
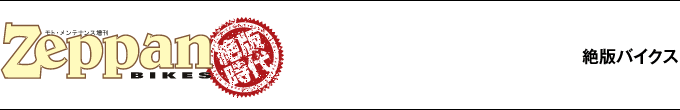
記事提供/2009年11月24日発行 絶版バイクス5

1966年、世界グランプリレースで「全クラス制覇」を成し遂げたホンダは、その年を境にWGPレースから撤退。その後、ホンダRSCが中心になり、市販車を改造したレーシングマシンの開発が進められた。CB750Rもその1台だ。


 会社の設立から10年も満たない50年代中頃、「世界グランプリ参戦宣言」を高らかに発表したのがホンダである。その後、59年にはマン島TTレースに参戦。その年から急激に技術力を高めたホンダは、翌60年には世界グランプリにも参戦。そして、参戦2年目の61年には初優勝を飾った。その後の快進撃は、レースファンならずとも知られるところだが、1966年、ホンダは全クラス制覇をもって世界グランプリの檜舞台から撤退。その後のレース活動は、ホンダRSCが中心となり行われるようになった。この頃から2輪も4輪も「市販車ベース」が中心になり、ホンダRSCはモータースポーツ分野の普及を目的に、ユーザーサポートを展開していったのだった。
会社の設立から10年も満たない50年代中頃、「世界グランプリ参戦宣言」を高らかに発表したのがホンダである。その後、59年にはマン島TTレースに参戦。その年から急激に技術力を高めたホンダは、翌60年には世界グランプリにも参戦。そして、参戦2年目の61年には初優勝を飾った。その後の快進撃は、レースファンならずとも知られるところだが、1966年、ホンダは全クラス制覇をもって世界グランプリの檜舞台から撤退。その後のレース活動は、ホンダRSCが中心となり行われるようになった。この頃から2輪も4輪も「市販車ベース」が中心になり、ホンダRSCはモータースポーツ分野の普及を目的に、ユーザーサポートを展開していったのだった。
そんな時代に登場したのがCB750Rである。市販車CB750のメインマーケットであるアメリカでは、レース活動での実績が販売数に直結。つまりレースで勝たなくては、好セールスを期待できなかったのである。そこでホンダRSCでは、アメリカホンダモーターからの要請も含め、CB750ベースのワークスマシンをデイトナ200マイルレース用に開発。同時にCB750Rキットとして、世界中のユーザーに向けたレーシングパーツの販売を開始したのだ。
ここに紹介するCB750Rは、そんな当時のワークスマシンを忠実に再現したもので、市販キットパーツはもちろん、当時のワークスパーツも組み込まれたデイトナ仕様である (現在はホンダコレクションホールに展示されている)。世界グランプリから撤退していた時期に開発されたマシンとはいえ、ホンダの「レーシング魂」を強く強く感じる1台だ。
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |












