

取材協力/日本ミシュランタイヤ株式会社 取材・文/中村友彦 撮影/真弓悟史 記事提供/ロードライダー編集部
取材・文/中村友彦 撮影/真弓悟史 記事提供/ロードライダー編集部
掲載日/2018年2月7日
2002年の発売以来、スポーツツーリングタイヤ市場で絶大な支持を集めてきた、ミシュランのパイロットロードシリーズ。その最新作として2018年から販売が始まる“ロード5”は、日常域での扱いやすさや耐摩耗性を重視しながらも、予想以上のスポーツライディングが楽しめるタイヤだった。
IMPRESSION
万能タイヤとして
全方位の性能向上を実現
近年のオンロード用ラジアルタイヤは、①峠道やサーキットでの運動性能を徹底追及した“ハイグリップ系”、②日常域での扱いやすさや耐久性を重視した“スポーツツーリング系”、③両者の中間的な特性を備える“ストリートスポーツ系”の3種に大別できる。そして②の分野で、世界中のライダーから支持を集め、他のタイヤメーカーがベンチマークとするのが、ミシュランのパイロットロードシリーズだ。2018年から発売されるロード5では、名称からパイロットの文字が消えたが、全天候型オールラウンドタイヤという思想は、パイロットロード4以前と同様のようだ。

だが、試乗会場でロード5と対面した僕は、パイロットロード4以前とは異なる外観の雰囲気に、そこはかとない疑問を感じることとなった。と言うのも、ロード5のトレッドパターンは、同社の製品で最もスポーツ指向が強いパワーRS的で、ミシュランならではのサイプを含めた溝の量は、パイロットロード4より減っているのだ。
となると、ロード5は従来のシリーズとは路線を変更して、スポーツ性重視の方向に舵を切ったのではないか? 当初はそう思ったのだが、実際に走らせると日常域の扱いやすさという面でも、パイロットロード4を上回る資質を備えていた。

今回の試乗では、ミシュランが新作ロード5と前作のパイロットロード4を履く試乗車を各3台ずつ用意。僕はその中から、VFR800FとMT-07に乗ったが、ロード5で最初に感心したのは、上質な乗り心地と盤石と言いたくなる安定感だった。この点に関して、僕はパイロットロード4に悪い印象を持っていたわけではないが、ロード5を履いたテスト車には、前後ショックを高級品に換装したかのような感触があって、路面の凹凸に進路が乱される気配がまったくない。続いて感心したのは、ウェット路面でのグリップ力だ。この点についても、パイロットロードシリーズは以前から抜群の性能を備えていたが、ロード5はトレッド面の溝の量が減っているにも関わらず、パイロットロード4と同等以上の安心感に身を任せて、ウェット路面で気軽にフルブレーキングが行える。

右が先代のパイロットロード4で、左が新作のロード5。こうしてふたつを並べてみると、明らかにロード5は溝が少ないけれど、トレッド面に刻まれた溝の量を示すグルービングレシオは、パイロットロード4が13%だったのに対して、ロード5は1%減っただけの12%
とはいえ、そうした要素に感心する一方で、僕がロード5で驚いたのは、やっぱり運動性能だった。この点は前作パイロットロード4とは、劇的に異なっていたのだ。
既存のパイロットロードシリーズに限った話ではないが、基本的にスポーツツーリングタイヤは、ドライ路面での運動性能に特化したハイグリップ系ほどは、コーナリングで無理が利かないものである。逆に言えばコーナリング中は、ある種の気遣いが必要になるが、ロード5は濃密な接地感を頼りにして、コーナー進入時はハードブレーキングができ、旋回中はどんどんバンク角を深くして行けるし、立ち上がりではかなり早い段階からスロットルを開けられる(パイロットロード4で同様のアクションをすると、ヒヤリとする場面が何度かあった)。
もっとも単純なグリップ力なら、同社のパワーRSやパイロットパワー3のほうが上だろう。でもロード5の運動性能は、スポーツツーリング系では間違いなくトップクラスだし、冬場の峠道やウェット路面では、パワーRSやパイロットパワー3を抑えて、冷間時から過不足ない接地感が得られるロード5が優位かもしれない。
冒頭のように、近年のオンロード用ラジアルタイヤは3種に大別できる。とはいえ、今回テストしたロード5のスポーツ性、そして2017年春に登場したパワーRSの守備範囲の広さを考えると、ミシュランの場合は3種の垣根が、いい意味で曖昧になっている気がする。従来のタイヤ業界の定説では、運動性能と耐摩耗性はトレードオフの関係にあるのだが、ミシュランのテストによるとロード5のライフは1万余裕で、車両や使い方によっては2万近く保つと言われたパイロットロード4と、ほぼ同等のようだ。
抜群のウェット性能は
磨耗が進んでも維持

ミシュラン独自のXST=Xサイプテクノロジーは、このロード5ではXST Evoに進化した。内側に向かってサイプ幅が広がる断面形状を採用していることで、磨耗が進んだ際も十分な排水性を確保している。なお3,500マイル(約5,600km)使用したロード5のウェット路面における制動距離は、パイロットロード4の新品時より短いという

ACT+=アダプティブケーシングテクノロジープラスは、パワーRSから継承した技術だ。直進安定性と旋回性を高次元で両立するため、トレッドセンターには柔軟性に優れるシングルプライ構造、サイドウォールには高剛性が獲得できるクロスプライ構造を採用している
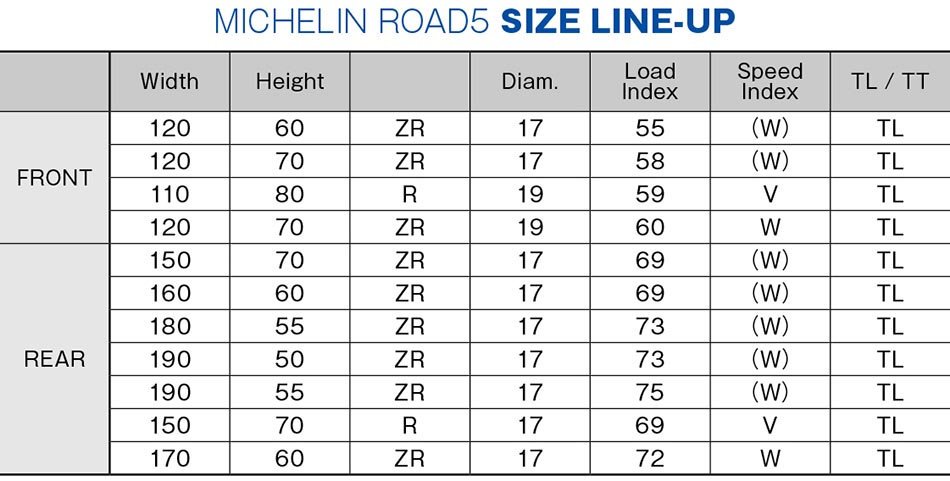
BRAND INFORMATION
1889年にフランスで設立された老舗タイヤブランド。自動車用・二輪車用など幅広い分野でタイヤを開発・販売している。欧州・北米・アジアに研究開発拠点を置き、世界170ヶ国以上に営業拠点も構えている。また、地図・ガイドブックの分野でも歴史は古く、グルメガイドとして名高い「ミシュランガイド」を20ヶ国以上で発行している。
 MICHELIN POWER RSは応答性の良さと温度レンジの広いグリップが魅力!
MICHELIN POWER RSは応答性の良さと温度レンジの広いグリップが魅力! 公道でもサーキットでもその走りは最高水準
公道でもサーキットでもその走りは最高水準 MotoGPのテクノロジーをストリートへフィードバック
MotoGPのテクノロジーをストリートへフィードバック モビリティの発展に貢献してきたミシュラン
モビリティの発展に貢献してきたミシュラン オフ志向のアドベンチャー用タイヤ ミシュラン・アナキーワイルド
オフ志向のアドベンチャー用タイヤ ミシュラン・アナキーワイルド ミシュランのニュータイヤ『パワー スーパースポーツEVO』インプレッション
ミシュランのニュータイヤ『パワー スーパースポーツEVO』インプレッション ミシュランタイヤ『パイロットロード4』試乗インプレッション
ミシュランタイヤ『パイロットロード4』試乗インプレッション