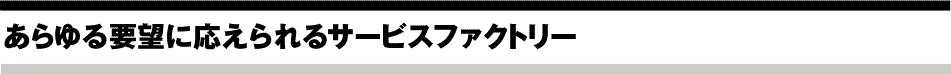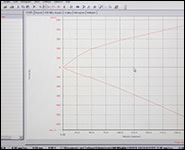Report:中村 友彦 Photo:富樫 秀明 記事提供:ROADRIDER編集部掲載日/2013年8月28日
アフターマーケットリヤショックは基本的にノーマル車への装着を前提に、各部の仕様を決定している。
つまり各部に手を加えたカスタム車にはその特性に応じたセッティングが必須事項となる。
日本でデータ取りを行うハイパープロでそのセットアップの基本を追う。
BRAND INFORMATION
右が企画担当のライター中村で、左がハイパープロ日本仕様の開発責任者である宇田さん。ふたりで意見を出し合いながらのセッティングは、約5時間に及んだ
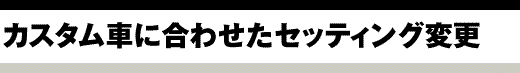
本誌連載の R/R ファクトリー企画・ZRX1200DAEG 編では、ハイパープロショックを新たに装着。その前段階として9月号で STD 車への装着を紹介したが、DAEG とハイパープロのマッチングは絶妙で、僕(担当・中村)はセッティングの必然性をまず感じなかった。では各部にカスタムを施した(ストライカー・フルエキやゲイルスピードホイールなどへ換装し車重は STD 比 15kg 程度軽くなっている。乗車姿勢も STD よりややスポーティ=前傾度が強い)、ファクトリー DAEG との相性はどうかと言うと……。
基本設定は的を射ているものの、ポン付けだと STD 車装着時ほど素晴らしくはないかなあ、と思わないでもなかった。具体的には、圧側減衰が低速/高速とも強めの印象で、自分なりにいじったフォーク(プリロード+1mm、圧側減衰を8→3クリック戻し、伸び側減衰を7→3クリック戻しに変更)とのバランスも、少々崩れているような気がする。
ハイパープロを含めたアフターマーケットリヤショックは、基本的に STD 車への装着を前提にしているのでこれは当然なのだけれど、さて、こういった場合はどう対処すればいいのだろうか。それを知るべく、ハイパープロの輸入販売元であるアクティブを訪れ、開発担当者の宇田知憲さんとともに、カスタム車へのセッティングに取り組んでみた。


サグの計測に入る前に、宇田さんはスイングアーム長(軸間距離)を計測。これが540mmと分かると、次はスイングアームピボットを軸にメジャーをそのまま扇状に回転させ、0G/1Gを計測する際に使用する任意のポイントを設定。0G/1Gの計測にはいろいろなやり方があるが、この手法が最も正確で確実なようだ
上の写真はテールカウルに任意のポイントを設定したもので、ピボットからの距離は540㎜。0G/1Gを計測する際は、この任意のポイント~リヤアクスルセンターを測るのがベストだが、DAEGの場合は右の写真の位置にメジャーの起点を引っかけたほうが、計測が行いやすかった
0G/1Gの計測に絶対的な正解はないが、ハイパープロは後輪の動き方を意識した手法を推奨。マニュアルに記載されたサグも、この手法が前提となっている
1G High/Lowローはいずれも車両を直立させ、テールまわりを支えた状態で計測するが、いったん持ち上げた後/いったん押し下げた後は、車両をそっと支えるだけで、テールまわりに力を加えてはいけない。マシンが倒れることが心配な場合は、ハンドルに手を添える助っ人がいてもいいが、その場合もフロントまわりに力を加えないようにする
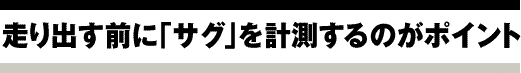
サグを計測して車体姿勢を調整
とりあえずポン付け状態で乗りますか? セッティングを始めるにあたって、僕はまずこう言ったのだが、宇田さんの答えは、「いえ。最初はサグの計測からです。これをやらないと、現状の車体姿勢が分かりませんからね。リヤショックのセッティングと言うと、すぐにバネやダンパーの話になりがちですが、一番大事なのは車体姿勢なんですよ」だった。
このサグ=1Gは、1名乗車時の車体沈下量で、サスストロークとすれば 20~30% 程度。サスセッティングの基本量となり、ライダーが跨った状態(乗車1G)での計測を推奨する場合もあるが、ハイパープロは空車状態が基本。実際の計測方法は上を参考にしてほしいが、スイングアームの動きを考慮した任意の計測点の設定方法と、1Gにハイとローの2種類があるという考え方は初体験だったが、どのショックをいじる際にも有効なはずだ。
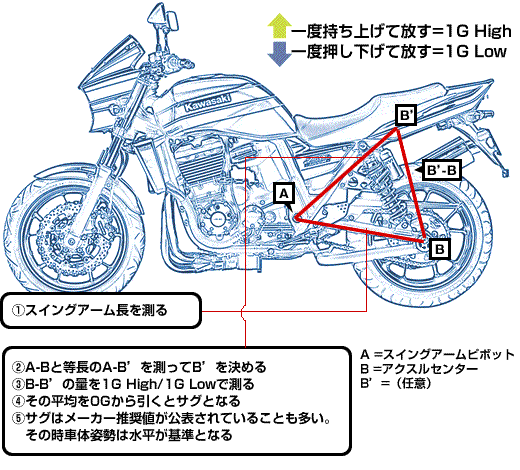
プリロードの調整でサグを推奨値の10㎜に
ハイパープロをポン付けした状態でファクトリーDAEGのB-B’を計測すると、0Gは434㎜で、1G High/Lowは425/421㎜だった。1Gの平均値は(425+421)÷2=423㎜だから、サグは0Gからこの平均値を引いた434-423=11㎜となる。続いてプリロードを1/2回転かけたところ、1GHigh/Lowは426/422㎜に変化。この状態での1Gの平均値は424㎜だから、サグは434-424=10㎜となった
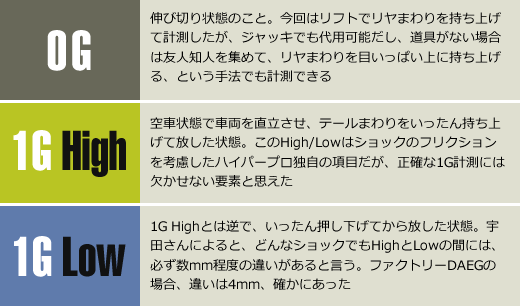
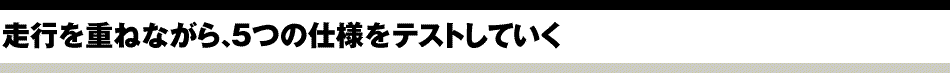



サスセッティングの実走テストは、ひとりよりふたりでやったほうが効率がいい(と言うか、楽しい)。もちろん、宇田さん(右)のようなエキスパートなら、ひとりでもベストセッティングに辿り着けるが、僕のような普通のライダーの場合は、自分の感覚に今ひとつ自信が持てないので、同じ条件で試乗して感想を言ってくれるライダーがいると、すごく助かる。とは言えテストライダーが3人以上になると、それはそれで混乱を招く原因になるので、やっぱり信頼できる感性を持った友人や知人とふたりでやるのがいいだろう
サスセッティングを行う際に欠かせないのがデータ取り。0G/1Gは言うまでもなく、宇田さんはすべての数値を記録していた
プリロードを+1/2回転
ポン付け状態でのサグは 11mm。ハイパープロの推奨値は 10±5mm なので、これなら許容範囲内だが、宇田さんは 10mm から始めるのがベストと考えているので、プリロードをアジャスター 1/2回転=0.75mm かけたところ、サグはきっちり 10mm となった。以下はこの状態でファクトリー DAEG に乗った、宇田さんの感想。
「バネレートとプリロードの設定はいい感触ですが、確かに中村さんの言う通り、フロントとのバランスがいまひとつですね。存在感が希薄なうえに、スロットルを開けるとすぐにフロントが上がろうとする。実は私は以前から ZRX シリーズのフォークの設定に疑問を持っていて、今回も STD のよくない面が出ていると思いますが、現状でハンドリングに悪さをしているのはリヤでしょう。具体的には、走行状態でスイングアームのタレ角が強すぎて、スイングアームピボットを上手く前に押せていない感があります。タレ角を弱めるためにはショック長を短くします。それで様子を見てみましょうか」
ショック長をマイナス0.5mm
タ、タレ角? 恥ずかしながら、そういう着眼点は微塵もなかった。しかし車高調整部でショック長を 0.5mm 短縮した状態で乗ると……。あららら、であった。まずスロットルがすごく開けやすくなったし、フロントフォークからのフィードバックが明確になったし(この感触を知ると、先ほどまではフォークを手加減して使っていた気がする)、おまけに乗り心地までよくなっている。
宇田さんが教えてくれた試乗コースには、路面の凹凸が激しい高速コーナーがあって、先ほどの状態でそこを通過する際は、スロットルを戻してやり過ごすしかなかったのに、現状だと加速状態を余裕で維持できてしまう。これは前後ショックがきちんと仕事をしていることの証明であると同時に、STDショックではおそらく実現できない世界だろう。
「最初の状態でスイングアームのタレ角が強過ぎると感じたのは、マフラーの交換によるバネ上の軽量化に加えて、ライポジという要素もあるでしょうね。ノーマルより前傾度が増した姿勢ですから、リヤに荷重がかかりづらくなっていた。ショック長を短縮したのはそれを補正するためで、言ってみれば、動的な車体姿勢を適正な状態にしたわけです」
伸圧ダンパーを抜く
作業としてはたったの2行程だが、それだけでファクトリー DAEG の乗り味は激変した。とは言え、これで僕が大満足しているかと言うと、現状ではハイパープロを満喫する土壌ができただけで、よくなる余地はまだありそうな気がする。個人的には、日常的なツーリングに使うには圧側ダンパーが強過ぎる気がしたので、そのことを宇田さんに告げると、「じゃあ乗り心地重視の方向でいじってみましょう。とりあえず圧側を低/高速ともに3クリック、伸び側を5クリック抜きますけど、減衰は伸びから決めて、圧はそれに沿う特性にするのが基本です。今回は時間がないので一気にいじりますが、ショックをいじるときは1回につき1カ所。これは減衰に限らず、プリロードやショック長にも言えることですね」との答えが返ってきた。
この調整後に試乗に出かけた宇田さんは戻って来ると、さらに圧側の高速を3、伸び側を3クリック戻しとして再試乗。最終的にハイパープロの出荷状態に対し圧側低速15→18、圧側高速15→21、伸び側25→33クリック戻しとなった仕様は、乗り心地が良い上に姿勢変化が分かりやすく、僕が想定するツーリングに最適と言える感触になっていた(ただ一方で、激しい凹凸のある高速コーナーでは、車体の落ち着きが少々悪くなった)。
さらにプリロードを+1/2回転
人間の欲望というのは切りがないもので、今回の作業を通してセッティングの面白さを体感した僕は、今度はもう少しリヤの踏ん張り感が欲しくなってきた。
これについて宇田さんは、プリロードをさらに1/2回転かける(出荷状態+1回転)ことで対処。何だか上手く行き過ぎの感があるものの、この変更も大正解で、ひとまず、これを今回の完成形とすることにした。
「これはこれでひとつの正解ですけど、走る状況やカスタムの度合いでベストセッティングは変わってきますから、今後もいろいろなことを試してみてください。僕からひとつお願いがあるとすれば……、ハイパープロのフォークスプリングを試してみませんか、ということですね。今回は現状のフォークに合わせるという方針でリヤショックを調整しましたが、フォークに手を付けていいなら、さらに1ランク上の世界が見えてきますから」というのが、今回の作業に関する宇田さんのまとめで、そう言われたら試さないわけにはいかないではないか。というわけで、次の段階となるその模様は次号以降の R/R ファクトリーで紹介する予定だ。