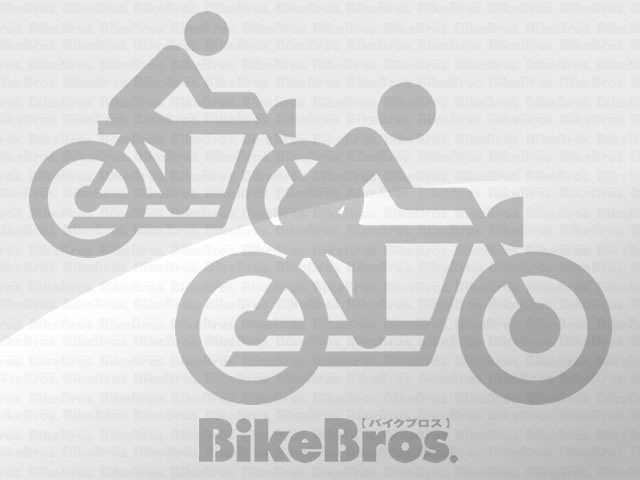Text / Kentaro SAGAWA Photo / Satoshi MAYUMI, Yuji FUKUYAMA, RAT 取材協力 /ライディングアカデミー東京
普段から役立つ実践的なノウハウや方法をレクチャーしてくれるのは、バイクライフをもっと豊かにするためのライディングスクール「ライディングアカデミー東京」の佐川健太郎校長。せっかく手元にある大型バイク、安全に走りを楽しみ、満面の笑みで1日を終えたいもの。そのためには、ライダー自身のスキルアップと安全意識の向上、環境へも配慮したスマートなライディングを目指したい。それが“スマートテク”なのだ。
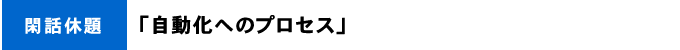
パートに分けて
正確に繰り返す
華麗な包丁さばきを見せながらカウンター越しにお客さんと談笑する板前さん。ブラインドタッチで目にも止まらぬ速さでキーボードを叩くオペレーター。彼らはいちいち手元を見なくても、ミスすることなく正確に仕事をこなしていきます。何故そんな離れ業ができるのでしょう?
それは長年のトレーニングによって、体がその動作を覚えているからです。いわゆる「体で覚える」というもの。バイクライディングも同じですよね。皆さんがバイクに乗っているときも、頭で手順を考えなくても、自然にブレーキ操作やシフトワークをしているはずです。
バイクは非常に高度かつ感覚的な乗り物です。エンジンの大部分はすでにコンピュータで緻密に制御されていますが、一方でライダー自身が体を使ってバランスをとらないと走れません。それでいて、人間の能力をはるかに上回る加速性能や旋回力、制動力を備えています。その意味で、バイクはライダーの能力を極限まで拡張するマシンとも言えるでしょう。であるならば、それを操る人間もまた能力を向上させていくべき、と私は考えます。
そのためには、我々ライダーも「体で覚える」をさらに高度化させ、状況に合わせて速やかに最適な操作・動作が出来るようになりたいものです。考えずとも自然に出来るようになること。これを私は「自動化」と呼んでいます。
「自動化」のプロセスとして大事にしたい3つのキーワードがあります。それは「細分化」「正確性」「反復性」です。たとえばブレーキングを上達させたいとします。その場合、まずやるべきことは、ブレーキングの要素を出来るだけ細かく分解してシンプル化すること。2輪車のブレーキシステムは通常、前後2系統2操作になっています。そこでまず、前・後のブレーキ操作を別々に分けてトレーニングします。ライダーはひとつの操作に集中できるため、正確な入力のタイミングや加減を覚えることが出来ます。さらに繰り返しトレーニングすることで、体にその動作・操作を刻みつけることが出来ます。
もうひとつのポイントは頑張り過ぎないこと。と言ってもダラダラやる、という意味ではありません。イメージとしては「気持ちよく走れる程度」。私はこれを「80%ルール」と呼んでいますが、どのスポーツでも全力の8割程度でトレーニングすると、高い効果が得られるそうです。逆に冷汗をかいたり、肩に力が入ってしまうのであれば頑張り過ぎ。特に一発のリスクが高いバイクの場合、そこまで追い込んで走ることに意味はないでしょう。
「自動化」が進めば操作以外のこと、たとえば路面のグリップにも気を配れるようになるでしょうし、万が一の場合でも体が勝手に動いて危険を回避出来るかもしれません。「自動化」はすなわち、安全にも直結するスキルなのです。
文/佐川 健太郎
自動化によって
危険回避能力も高められる
 ブレーキングのトレーニングの中には、回避制動というものがあります。目標に向かって直線を加速しつつ、信号やサインマンの指示に従って目標直前で右か左にかわし、制動・停止するもので、人やクルマなどの急な飛び出しを想定したトレーニングです。危険が発生したという素早い認知、どちらに避けるかの正確な判断、車体を傾けて進路を変えるための的確な操作などが求められます。
ブレーキングのトレーニングの中には、回避制動というものがあります。目標に向かって直線を加速しつつ、信号やサインマンの指示に従って目標直前で右か左にかわし、制動・停止するもので、人やクルマなどの急な飛び出しを想定したトレーニングです。危険が発生したという素早い認知、どちらに避けるかの正確な判断、車体を傾けて進路を変えるための的確な操作などが求められます。
瞬間的にバイクの向きを変えるためには、体重移動、ステップワーク、逆操舵などのテクニックを駆使していきますが、「こういう動作・操作をやろう!」と考えていては間に合いません。そこで必要になってくるのが「自動化」のプロセスです。初めは低い速度で、サインマンも余裕を持って指示を出します。繰り返しトレーニングを行うことで、まるで頭の中で回路がつながるように、スムーズに回避行動がとれるようになっていくから不思議。最終的には反射的に体が反応出来るようになります。
もちろん、回避制動などしなくて済むに越したことはありませんが、もしものときの備えとして、体得しておきたいスキルではありますね。
| ライディングフォーム 大型バイクの強大な加速力に対応するためには、前傾フォームは欠かせません。普段から加速時は上体を前に傾けることを習慣にしていれば、スロットルを開けたときに意識しなくても自然に加速フォームがとれるようになります。ブレーキング時は逆に上体を起こしつつ、自然とニーグリップで体を支えられるようになればしめたもの。「自動化」によって最適なフォームを作れるようになります。 | Uターン Uターンのプロセスは「車体を倒し込む」→「ステアリングが切れる」→「一定速度でターン」→「車体を起こして加速」となります。この中で最も難しい部分が「一定速度でターン」。操作系のポイントはスロットルと半クラ、リアブレーキをなるべく一定に保つことですが、そこで「自動化」が役立ちます。直線を使ってこの3つの操作感覚を体に刻みつけてしまうことが、Uターン上達の早道です。 |
| ブレーキリリース コーナー進入ではフロントブレーキを若干残したまま倒し込んでいくことがあります。このとき大事なのはブレーキリリースのタイミング。ポンッとレバーを放してしまえばフロントフォークは伸び上がってしまい、曲がるキッカケを得られず、逆に握り込んだままだとフロントから転倒するリスクが高まります。バンク角に応じてスムーズにリリースしていく感覚は「自動化」によってもたらされます。 | 倒しこみ ストレートからコーナーに向けて倒し込んでいくプロセスは、主に「加速」→「準備(腰ずらし)」→「ブレーキング」→「シフトダウン」→「倒し込み」から構成されています。この5段階の流れをスムーズに組み立てていくためには、やはり「自動化」がキモ。これが出来ていないと、コーナー進入でバタバタと忙しく、順番も乱れてしまいがちで、安定したアプローチが出来なくなります。 |

-
【前の記事へ】

閑話休題「ライディングスタイルを考える」 -
【次の記事へ】

閑話休題「スポーツライディングの醍醐味を味わおう!」
こちらの記事もおすすめです
この記事に関連するキーワード
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!